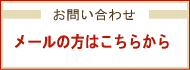雪山レイヤリング
実例(私の場合)
・八ヶ岳・赤岳登頂
|
・肌着 詳しく見る
・メンズ・キャプリーン2(パタゴニア)
・ウール素材のもの
・中間着 詳しく見る
・アコンカグア・フーディー (マムート
・アコンカグア・ジャケット (マムート)
・R1フーディー (パタゴニア)
・中間着のさらに上に 詳しく見る
・----・ベスト (マムート)
・ナノ・パフ・ベスト (パタゴニア)
・アウター 詳しく見る
・アルバロン・ジャケット(マムート)
・アイシクルジャケット(ノースフェイス)
・防寒着 詳しく見る
・ウィンドストッパー・ディライト・ジャケット (マムート)
・メンズ・ナノ・パフ・フーディー (パタゴニア)・
・手袋 詳しく見る
・エキスパート・ツアー・グローブ (マムート)
・-----(ヘリテイジ)
・------(パタゴニア)
|